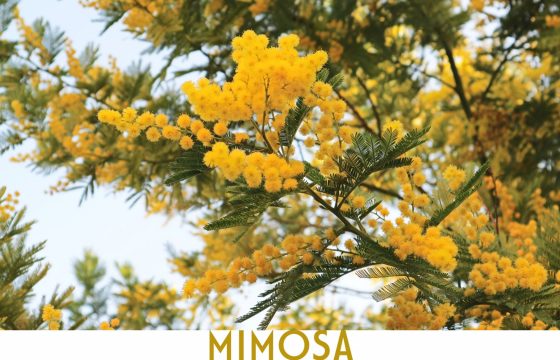NEWS / Sep 23, 2022#500#500X#panda#イベント500eフィアットピクニック静岡県の浜名湖ガーデンパークに全国各地から1,000台を超えるフィアットとアバルトが集結し、『Nuova 500』生誕65周年を祝う『FIAT PICNIC 2022』が開催されました。会場中央にあるステージで行われたさまざまなコンテンツから、同時に開催されていたアクティビティまで、今回のイベントの模様を自動車ライター嶋田智之さんにレポートしていただきました。 FIAT PICNIC 2022にようこそ! 「みなさん、こんにちは!FIAT PICNIC 2022にようこそ!」 9月10日の朝10時。浜名湖ガーデンパークに、MCをつとめるお笑いタレントのレギュラーのおふたりの声が響き渡ります。フィアットファンのための恒例のイベントは、ここ数年はコロナ渦を鑑みて規模を縮小したり、かたちを変えたりしての開催でしたが、今回は例年どおりの大規模開催。受付けがはじまる30分前の朝8時には約900台を想定したメインの駐車エリアはほぼ埋まり、受付け開始と同時に長い列ができていました。みなさんがどれほどこの日を楽しみにしていたかが伺えます。のちに判ったことですが、この日この場に集まったフィアットとアバルトは約1,000台、参加人数も2,000人オーバー。フィアットのイベントとしては世界最大級といっていいでしょう。 開会式のステージにはフィアットのブランドアンバサダーをつとめるティツィアナ・アランプレセさん、ステランティスジャパンのマーケティングダイレクターであるトマ・ビルコさん、同じくフィアットブランドマネージャーの熊崎陽子さんが登壇。レギュラーのおふたりの思わずクスリとさせられてしまう軽快なトークでスタートし、それぞれご挨拶です。 ▲左から、レギュラーのおふたり、ティツィアナ・アランプレセ氏、熊崎陽子氏、トマ・ビルコ氏 まずはティツィアナさんが、今年が『Nuova 500(ヌォーヴァ チンクエチェント)』のデビューから65年目となることにからめ、「私たちはずっとECOを大切にしてきました。今年からは『500(チンクエチェント)』に電気自動車ができたので、将来に向かってヘリテージを大切にしながら、サスティナビリティをもっと大切にしていきたいです」と、『500e(チンクエチェントイー)』の存在の重要性を伝えます。「このイベントはフィアットとアバルトのファミリーイベント。15年も続けてきたので、はじめの頃は小さかったお子さんもすっかり大きくなりました。フィアットに乗る人たちは若々しいです。心がとても若い。それはフィアットLOVEだから、ですね」とフィアット愛の強さをのぞかせました。 フレンチブランドに携わった時間が長いトマさんは、「初めてこのイベントに参加したんですが、朝からみなさんのポジティブなエナジーを感じて、とても感動しています。フィアットオーナーの人たちはすごい。熱いです」と、驚いていた様子でした。「私はまだ勉強しなきゃならないことがたくさんあるから、みなさん、私をつかまえていろいろ教えてください」という言葉には、拍手を送る参加者の姿も。 同じく初参加の熊崎さんも、「この日を楽しみにしていました。こんなにたくさんの色とりどりのフィアットを見て、みなさんの笑顔を見て、本当に感動しています」と、ニコやか。「これからもフィアットはサステナブルな活動と女性を応援し続けるブランドでありたいと思っています。ハッピーで楽しいイベントやキャンペーンを今後も企画していきます。楽しみにしていてください」と嬉しいコメントをくださいました。 そして開会式の最後に、参加者全員で記念撮影。地上からとドローンからの2パターンの撮影が行われました。数え切れないほどのフィアット乗りがギュッと集まる光景は圧巻です。 “誕生会”をテーマとしたコンテンツスタート! 記念撮影が終わると、いよいよイベントが本格的にスタート。まずは『FIAT♡PETSファッションコンテスト』です。今年のドレスコードは“誕生会”。フィアットのクルマたちが愛玩動物っぽいからなのか、あるいはペットっぽいからフィアットを選ぶのか。フィアット好きには動物好きが多いようで、愛らしい衣装で着飾ったワンちゃんたちの姿をやさしい笑顔で見つめる人の多かったこと。とてもフィアットらしいあたたかな催しだな、と感じました。 続いては『フィアット デコレーションコンテスト』。ステージの両サイドに5台ずつ、“Forever Young”をテーマにデコレーションされた『500』&『500X』が並んでいます。思い思いのセンスやアイデアで飾られたクルマたちはなかなか見もので、カメラを向ける人も多々。8月にインタビューさせていただいたフラワーアーティストの鵜飼桃子さんもお友達といっしょに参加していて、クラシック『500』を生花で彩った作品は注目を浴びていました。ほかにもルーフの上でピクニックを表現しているクルマあり、浦和レッズ仕様のクルマあり、人気キャラクターに変身しているクルマあり、と賑やかです。はたして栄冠は誰の手に……? お昼になると、世界的なバイオリニストであり、フィアットの熱心なファンでもある古澤巌さんの生演奏がはじまりました。芝生エリアには参加者のみなさんがたくさんのテントを張っていたのですが、美しく澄み渡る感動的な音色に、ほとんどの人がテントから出て聴き入っていたほどでした。 ステージの裏でも大盛り上がり!出展ブースもご紹介 総合受付の近くに長い列ができていました。見に行くと、柴野大造さん率いる“MALGA GELATO”のジェラートが、参加者に配られていました。強烈に暑かったこの日、世界が認めた美味なるジェラートは、一服の清涼剤どころか天国に感じられたことでしょう。 ワークショップも人がひっきりなしです。間伐材から抽出した精油でアロマスプレー作りを体験できる『MEGURIWA』。ハーバリウム作りの『KEI FLOWER』、手染めバッグ作りの『山口屋染房』、木製カレンダーやペン立てを作る『ヒゲゴニア』といった、浜名湖ガーデンパークが展開するワークショップを招いたFIAT × HAMANAKOのコーナー。お子様たちが塗り絵を楽しめる『CIAO! BAMBINA ARIA』。体験というのは旅を何倍にも楽しくしてくれるもの。笑顔で手を動かす人たちで常に満員でした。 […]






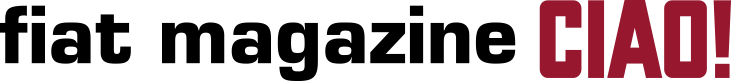









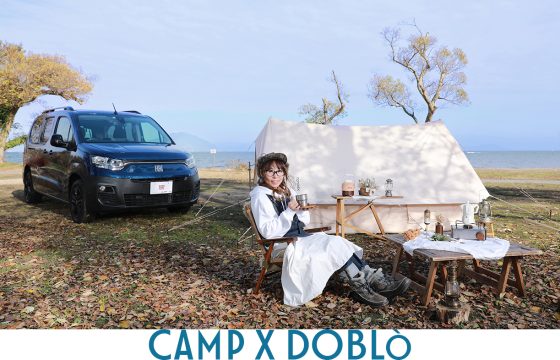















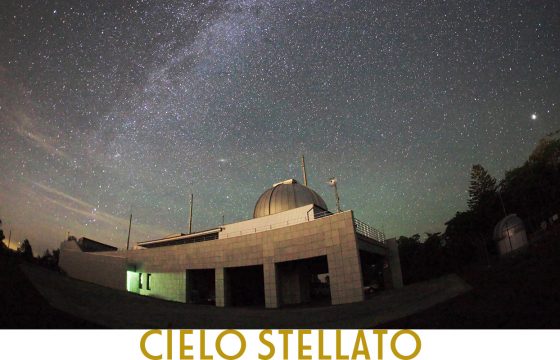


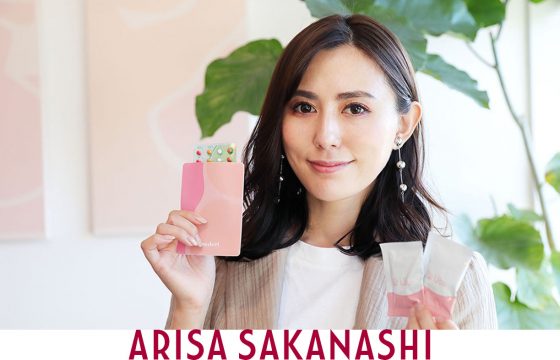

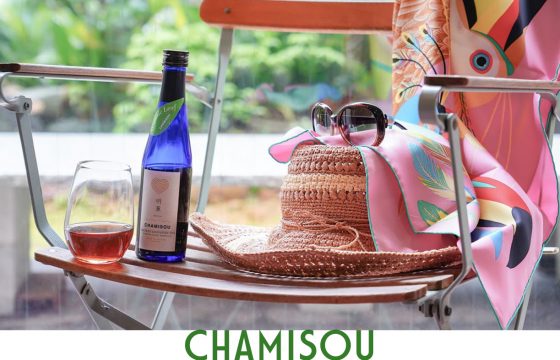













-560x360.jpg)